 越沢稲荷の大スギ 幹周り6.05mと |
 新柵山山頂 三等三角点で基準点名 西平 |
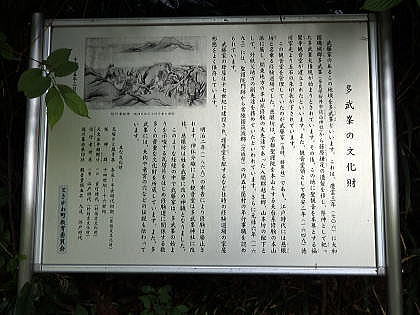 多武峯の集落の・・・ |
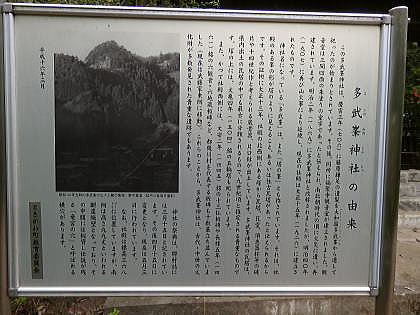 多武峯神社の・・・ |
| 比企・旧都幾川村の山 新 柵 山 490.09m |
 越沢稲荷の大スギ 幹周り6.05mと |
 新柵山山頂 三等三角点で基準点名 西平 |
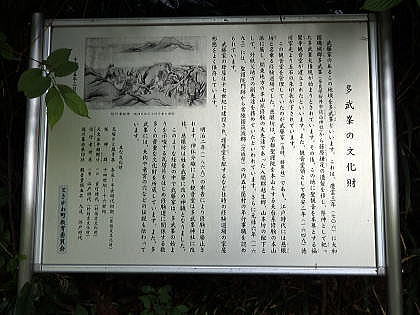 多武峯の集落の・・・ |
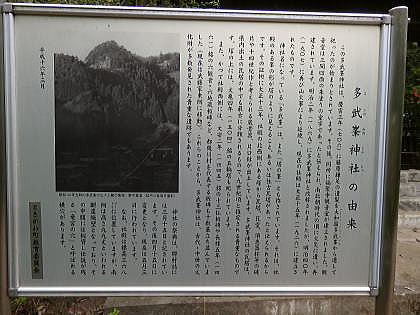 多武峯神社の・・・ |
奥武蔵グリーンラインの檥峠の北にある丸山(833m)から北東に伸びる尾根は高度を落しながら676.1mの風早山を経てこの新柵山に至っている。三等三角点で基準点名 西平が設置されている。
奥武蔵流域を流れる川は、北の規川、この山裾を流れる都幾川、越辺川、高麗川を併せた本流?の名栗川が入間川と名を変え、江戸時代前期までは直接、東京湾に流れこんでいた。いずれも結構な難読地名である。
現在は入間川は川越市東部で荒川に合流しているが、江戸時代の頃までは、この関東平野南部(武蔵の北部)はこの入間川、荒川、利根川、渡良瀬川が平野に落ち込み、巨大な三角州の地形のように四方八方に分流して大湿地となっていた。家康はその分流の多くを集約して改修し、残りは平野の用水路として整備したようだ。古利根川や元荒川という名で本来の?流れの名が残っている。
東京のハイカーが訪れる奥武蔵の大半はこの入間川の流域になり、西武池袋線、東武東上線沿線の山々となっている。又、この新柵山の中腹には平安時代以降、何度か戦乱の舞台としても登場する大和・桜井の多武峰にある談山神社から706年(慶雲3年)に藤原鎌足の遺髪を遷して建立した多武峯神社があり、福聚寺の観音堂もあるという。
世間では今日が今年のGWの初日だというし、関東では午後から天候が不安定になるという。渋滞も考え、6時前に出て、午前中には下山しよう。
鶴ヶ島までは順調で、その先で事故渋滞のようだが、ハマる手前で高速を降り、ときがわ町の「くぬぎ村交流体験館」に7時10分過ぎに到着した。ハイカー等の施設利用者外にはわずか離れた駐車場が案内されている。新柵山への標識は無い。
登山口を求めてわずかに先に進むと、右手の斜面に細い踏み跡があり、「七曲り」とあったと思う。「これだろう」と登ると急斜面に細かなジグがあり、その角毎に「一」から「七」までの小さな板が立っている。これが七曲りなのだろう。
登り切り、わずかに右手に進むと一間四方ほどの「浅間神社」がある。その先には道が無いので少し戻ろうかとすると、お堂の直前で折り返すように登る踏み跡があり、上の畑地と物置の間を抜けるとやや広い草道に出た。ここにも「くぬぎの七曲り」の旗がある。特に標識はないが、先に進むと「前山行 稲荷前」という丸いバス停のような標識があり、「越沢稲荷の大スギ」がある。2002年の計測で幹周りが6.05mであったと記載されている。
山道は尾根を左手にして巻き気味に進むようになり、up downの無いおだやかな道になり、尾根?に出たあたりに初めて新柵山への標識が現れた。道は緩い尾根で、「木の村」を象徴するような杉林の中にクネクネと踏み跡が続き、小鞍部から一登りをすると「刀爾の頭」という482mの標高点のある頭に着いた。ここも杉林の中である。
次の小鞍部は新柵峠、西方の八木成と東方の馬生や野中を繋ぐ峠で、多武峯への標識もある。下山はここからだ。最後の登りは今日一番のものであるが、標高差はたかだか40m余りでノッペリとした高みに出たが山頂ではない。わずかに下り登りをすると、「さっきの方が高いぞ」と思えるような所に山頂標識と基準点名「西平」の三等三角点が鎮座していた。
曇天のせいだけでなく、杉林の中の山頂の為に展望は皆無である。休憩中にトレランの若者が、一人、二人と駆け抜けていった。この山中で会ったのはハイカーはゼロ、20代~30代のランナーが全部で6人であった。
峠まで戻り、多武峯への道に入った。道はしっかりしているもののトレランコースから外れているせいか、小枝や杉の葉が散乱している。峠から15分足らずで舗装車道に出た。「南登山口」とあり、西にはくぬぎ村、東には0.2kmで「多武峯」とある。
多武峯は即ち多武峯神社であると思い込んでいた。地形図で神社はこの車道の何処からか右に派生する尾根上にある。緩く車道を登るともう下りになる。「おかしいな?」と戻るがやはり尾根道はない。
もう一度峠?状から下ると先に建物が見える。「何だあれか!!」と進むと、路肩に軽自動車が停めてあり、そこからほぼ水平に車が困難そうな道が分かれ、立派な門のある建物に出た。庭のある門を潜るが、中の建物は廊下に洗濯物が干してあり、神社ではなく、民家のよう。
直前には「多武峯の文化財」という説明版もあり、多武峯は地名であったようだ。付近をウロウロしたものの結局、今日第二の目的地であった神社には辿りつけず、下山地まで戻り、この車道をくぬぎ村の駐車場まで戻る事にした。道端には予想以上に多くの民家があり、ゆっくりではあるが、30分近くかかって駐車場に戻った。
「このままで終わらせる訳にはいかない。きっとあの辺に神社があるはずだ」と今歩いてきた道を車で戻る事にし、南登山口を過ぎ、軽自動車の駐車場所を過ぎると、すぐに細い車道が右下に分かれ、「多武峯神社」の標識があるではないか。2.5mほどの幅の車道を少し下ると、2台分ほどの空地があり、山道?が分かれている。「これに違いない」
車を停め、山道に入るとすぐに鳥居があり、「参道?」が始まり、尾根の右手を絡みながら進み、回り込んだ先からは鎖付の石段となり、「多武峯神社」があった。この地は標高368mで東方の集落からは岩峰の頭にあたるのだという。
645年の大化の改新の前の蘇我入鹿を殺した「乙巳の変」の前、中大兄皇子と中臣鎌足が話し合ったという大和・桜井の多武峰の談山神社、鎌足の遺髪が納められたという談山神社が何故この地にも祀られたのだろうか?・・・・・・。
〇 2025年4月26日 〇 天候 曇り
くぬぎ村交流体験館7.30浅間神社7.37越沢稲荷大スギ7.43~45 刀爾の頭8.04~08新柵峠8.14新柵山8.27~43新柵峠8.51~52車道・南登山口9.05~30(多武峯集落付近ウロウロ)くぬぎ村駐車場9.57
車で移動―多武峯神社入口駐車場所10.10多武峯神社10.17~2駐車場所10.26
2025年の山へ
 登りのスタートは「くぬぎの七曲り」から |
 尾根に出るとこんな |
 482m真新しい山名板 刀爾の頭 |
 山頂 展望はない |
 |
 |
 |
 徒歩で見つけられず 車で動くと |
 多武峯神社 |